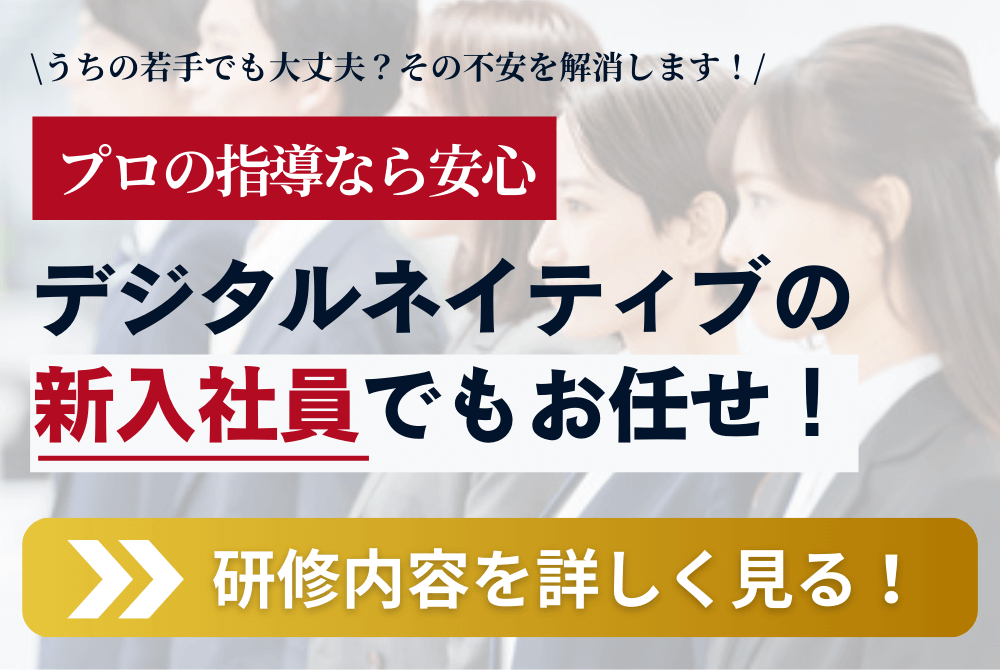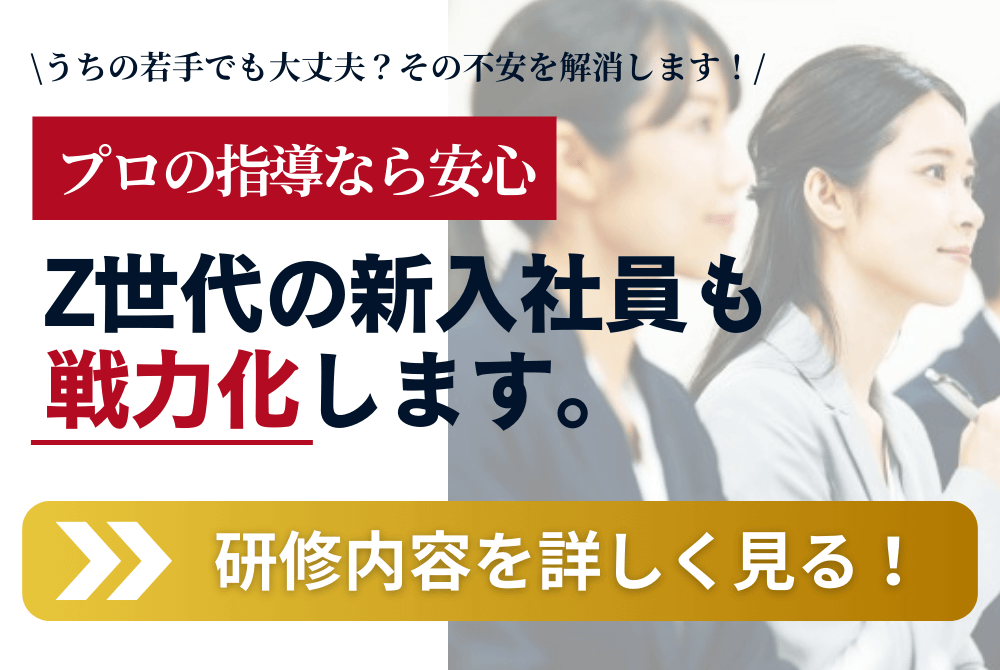本記事は、新入社員の電話応対に課題を感じていて、新入社員研修を外部に依頼するかを検討している事業者の方向けに、株式会社新規開拓の「電話応対向けの新入社員研修」に関する取り組み事例を紹介しています。
※実際の関係者が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.事務職新入社員が「基礎的な電話応対スキル」を身に付ける事を目的とした研修事例
大手ハウスメーカーA社が、新入社員に「基礎的な電話応対スキル」を身に付けてもらうために、外部研修を導入した事例です。
| A社の業種 | 大手ハウスメーカー |
|---|---|
| 受けた人の職種 | 一般事務(新入社員) |
| 受けた人数 | 15人 |
| 解決したい課題・実施の目的 | 電話応対に不慣れなZ世代の新入社員に、電話応対の基本的なスキルを身に付けさせること |
| 研修会社を選んだ「基準」 |
|
| 研修内容 |
|
| 研修の効果 |
|
1-1.研修で解決したい課題・実施の目的
ハウスメーカーのA社では、Z世代の新入社員が、電話でのやり取りに慣れていないことが課題となっていました。
Z世代の新入社員は、SNSやメッセージングアプリといった文面でのコミュニケーションを中心としているので、電話応対のような声でのコミュニケーションに苦手意識や恐怖心を抱えていたようです。
緊張感が声や話し方に出てしまい、顧客からの問い合わせや取り次ぎにうまく対応できず、クレームにつながるケースも発生。
A社は、新入社員に「電話応対の基本的スキル」を身に着けさせることで「電話応対への恐怖心や苦手意識を払拭」することを目的に、電話応対の外部研修を導入しました。
1-2.研修会社を選んだ「基準」
A社は以下の基準で複数の研修会社を比較検討しました。
- Z世代向けのアプローチに強みがある
- 実践的な練習で、「頭でわかるのではなく、実際にできる」レベルになることをゴールとしている
- 電話応対の基本から応用まで対応する研修プログラムを提供している
Z世代の特徴をよく捉えていることと、
単なるインプットではなく、ロールプレイングをはじめとした実践的なカリキュラムを繰り返し行うプログラムで、「自然と身体が動く」レベルになることをゴールとしている点に魅力を感じた研修会社を選びました。
また、対象者のレベルに合わせた研修プログラムを組めることも、選んだ決め手の一つです。
1-3.研修でどんなことをしたか
今回の研修では多岐にわたるプログラムを実施しており、下記にその一例を紹介します。
| 研修内容 | 信頼を築く心構えを身につける |
|---|---|
| 詳細 | 電話応対の基礎として、「声」で信頼を築くための心構えを徹底的に身につける。 |
| 研修内容 | スムーズな電話応対のための情報整理術の解説 |
| 詳細 | 相手からの要望や質問等にスムーズに対応できるよう、情報を整理する力を身につける。 |
| 研修内容 | クレーム対応等、高度な状況を想定したロールプレイング |
| 詳細 | 一般的によくあるシーンから、クレーム対応といった高度な状況を想定したロールプレイングで苦手意識を払拭。 |
このように、実践的な内容を中心に、繰り返し練習とフィードバックを行い、研修を通じて電話応対スキルを確実に身に着けられます。
1-4.研修の効果
研修後、A社からは「現場で自信を持って電話応対をしている姿が見られるようになった」という報告をいただきました。特に効果が大きかった3点について、A社の所感として紹介します。
A社が感じた効果①
「企業の窓口として安心して電話を任せられるようになった」
研修前は電話応対に対して恐怖心や不安があり、できるだけ避ける傾向がありました。しかし、研修で電話応対の基礎から徹底的に落とし込まれることで自信がつき、顧客との信頼関係を築けるまでになったので、今では「企業の窓口」として電話を任せられるようになりました。
A社が感じた効果②
「情報を正確に理解できるようになった」
以前は、顧客からの問い合わせ内容をうまく理解できず、何度か聞き返したり、スムーズに取り次ぎが行えなかったりするケースが多く見られました。研修後は、相手の話していることへの理解力が高まり、より正確に情報をキャッチできるようになりました。
A社が感じた効果③
「イレギュラーな場面でも落ち着いて対応できるようになった」
以前は、自分が分からないことへの問い合わせや、知らない企業からの営業電話などがかかってくると戸惑っている様子が見られました。
しかし、研修での実践的なプログラムを行ったことで、さまざまな問い合わせに対して臨機応変に対応できるようになりました。また、クレームといった高度な内容でも屈せずに対応できるまでに成長していました。
1-5.その後
2.通販会社の新入社員が「スムーズに電話応対ができるようになること」を目的とした研修事例
中堅通販会社のB社の新入社員のオペレータースタッフが、スムーズな電話応対ができるようになることを目的に外部研修を導入した事例です。
| B社の業種 | 通販会社 |
|---|---|
| 受けた人の職種 | オペレーター |
| 受けた人数 | 20人 |
| 解決したい課題・実施の目的 | 顧客からの注文電話にスムーズに電話応対できるようにすること。 |
| 研修会社を選んだ「基準」 |
|
| 研修内容 |
|
| 研修の効果 |
|
2-1.研修で解決したい課題・実施の目的
新入社員のオペレータースタッフが、電話応対の苦手意識を克服し、スムーズな応対ができるようになること。
通販会社のB社では、新入社員のオペレータースタッフが電話での会話経験が不足していることを課題に感じていました。
特に、「声が暗い」「ボソボソ話す」などの癖から、顧客とのやり取りに支障をきたす恐れがありました。
例えば、高齢の顧客の場合、ゆっくり大きな声で話すことが重要です。
また、顧客の名前や住所、注文された商品名など、正確に把握しなければならない情報や送付方法などこちらから伝えなければならない情報もあります。
うまく情報が伝達できなかった場合、クレームに発展しかねません。
B社は「声や話し方を改善することが、正確に仕事をこなすために必須」と考え、外部研修を導入しました。
2-2.研修会社を選んだ「基準」
B社は以下の基準で複数の研修会社を比較検討しました。
- 学んだことを現場で確実に再現できるようにすること
- オペレーターの職務特性に適合すること
- 電話応対の基本から応用まで対応するプログラムを提供している
現場を想定したシミュレーションを取り入れた実践的な研修内容で、電話応対における経験不足を補えそうと感じた研修会社を選びました。
過去にもさまざまな企業の研修実績があり、信頼感もありました。
2-3.研修でどんなことをしたか
今回の研修では多岐にわたるプログラムを実施しており、下記にその一例を紹介します。
| 研修内容 | 声と連動する表情の作り方・言葉遣いの指導 |
|---|---|
| 詳細 | 声の印象を良くするための、ボイス&トーントレーニングを繰り返し、実践経験を積む。 |
| 研修内容 | 電話応対前の必携ツール・情報整理術の解説 |
| 詳細 | スムーズな電話応対のための必携ツールと情報整理術を覚え、相手からの質問や要望を正確に把握できるようにする。 |
| 研修内容 | 多様なシーンに対応する実践シミュレーション |
| 詳細 | 一般的によくあるシーンから、クレーム対応といった高度な状況を想定したロールプレイングで苦手意識を払拭。 |
声のトーンや言葉遣いなどを基礎から学び、実践シミュレーションを交えながら、現場ですぐに使える応対力を身につけられる研修内容です。
2-4.研修の効果
研修後、B社からは「窓口担当としてスムーズに応対ができるようになった」とのご共有をいただきました。その中でも特に効果が大きかった3点について、B社の所感として「実際の声」をもとに紹介します。
B社が感じた効果①
「明るい応対ができるようになった」
暗いトーンやボソボソした話し方が改善され、明るい声・表情での応対が定着。顧客に「しっかり伝える」ことの重要さを再認識したようで、相手により伝わる声ではっきり話す社員が増えました。
B社が感じた効果②
「情報を正確に理解できるようになった」
研修前は、顧客の注文を聞き取ることに必死で他のことに手が回らない状態でした 。
しかし、研修後はメモを取りながら話を聞く、相手の言ったことを復唱するなど、情報を正確に把握しようとする意識が感じられました。
B社が感じた効果③
「落ち着いて対応できるようになった」
これまでは、顧客からの問い合わせに対して答えられない場面で考え込んでしまい、対応に時間がかかることもありました。研修を受けたことで、分からないことがあればすぐに周囲に確認する癖が身につき、迅速に対応できるようになりました。
2-5.その後
オペレータースタッフは、B社にとって顧客と会社との最初の接点であり、「スムーズな応対ができるスキル」は印象を大きく左右する重要なポイントであると再度認識したので、今後も新入社員研修の必須プログラムとして継続導入する予定です。
3.新入社員の「電話応対スキル向上」による、コールセンターの品質向上を目的とした研修事例
コールセンターC社が、新入社員のオペレーターに、高い電話応対スキルを身につけさせ、コールセンター全体のサービス品質を向上させることを目的として、外部研修を導入した事例です。
| C社の業種 | コールセンター |
|---|---|
| 受けた人の職種 | オペレーター(新入社員) |
| 受けた人数 | 20人 |
| 解決したい課題・実施の目的 | 高い電話応対スキルを身につけさせ、サービス品質を向上させたい。 |
| 研修会社を選んだ「基準」 |
|
| 研修内容 |
|
| 研修の効果 |
|
3-1.研修で解決したい課題・実施の目的
高い電話応対スキルを身につけさせ、サービス品質を向上させたい。
コールセンターC社では、新入社員のオペレーターが間違った敬語を使っていることや語彙力が乏しいことに課題を感じていました。
実際に業務中、電話応対ではご法度とされる「もしもし」などの言葉が聞こえ、相手に対して失礼な印象を与えている社員も見られます。
また、クレーム応対では相手の口調が強く、怯んでしまい、黙り込んでしまう社員もおり、応対に時間がかかるケースも発生。
C社は「電話応対はビジネスの基本であり、オペレーターが顧客と円滑にコミュニケーションを取ることが、サービス品質の向上に直結する」と考え、入社後早期にこれらのスキルを養うために研修を導入しました。
3-2.研修会社を選んだ「基準」
C社は以下の基準で複数の研修会社を比較検討しました。
- 印象ダウンを防ぐ「口癖」の改善をしてくれる
- 高度な状況を想定したロールプレイングを行っている
- 反復練習を行い、確実に身につくようにしてくれる
特にC社が重視したのは、相手に好印象を与えられる言葉遣いが身につけられる点です。さらに、受講後すぐに活用できる実践型のカリキュラムが豊富な点にも魅力に感じました。
3-3.研修でどんなことをしたか
今回の研修では多岐にわたるプログラムを実施しており、下記にその一例を紹介します。
| 研修内容 | 印象ダウンを防ぐ「口癖」の改善を目指したアクティブラーニング |
|---|---|
| 詳細 | 基本的な丁寧語や尊敬語、謙譲語を学び、正しい言葉遣いを徹底的に身につける。 |
| 研修内容 | 高度な状況を想定したロールプレイング(クレーム対応編) |
| 詳細 | 一般的によくあるシーンから、クレーム対応といった高度な状況を想定したロールプレイングで苦手意識を払拭。 |
| 研修内容 | 反復練習と質疑応答セッション |
| 詳細 | 苦手とする部分を繰り返し、練習することで確実に「できる」ようにする。 |
反復練習で、知識を理解するだけでなく現場で即実践できる行動スキル として定着させることを重視しました。
3-4.研修の効果
研修後、C社からは「現場で実際に変化が見られた」との報告をいただきました。
その中でも特に効果が大きかった3点について、C社の所感として「実際の声」をもとに紹介します。
C社が感じた効果①
「敬語や語彙力が向上した」
新入社員のオペレーターは、敬語や語彙力に自信を持てるようになり、電話対応時の不安が解消されました。
また、発声の仕方など基礎中の基礎も叩き込まれ、適切な言葉遣いに加え、明るい応対も身についたので顧客満足度の向上につながりました。
C社が感じた効果②
「クレーム対応ができるようになった」
以前はクレーム対応に対して苦手意識がありましたが、研修でロールプレイングを繰り返すことで、怯むことなく、自信を持って適切な対応ができるようになりました。
C社が感じた効果③
「素早い受け答えができるようになった」
研修前は、相手からの問い合わせにうまく答えられず、何度も説明し直したり、顧客との話をうまく切り上げることができず、応対時間が無駄に長くなったりするケースが見られました。
しかし、研修での反復練習のおかげで、素早い切り返しができるようになり、一人ひとりの応対時間が短くなったように感じます。
3-5.その後
コールセンターの新入社員が、「電話応対に必要な基本スキルをしっかりと学べる研修内容で、顧客の満足度やサービス品質の向上に繋げられた」と、ご満足いただけました。
また、「口癖の改善」や「クレーム対応」に関するトレーニングが大きな効果を生み、参加者全員が自信を持って電話応対に臨めるようになりました。